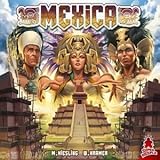重量級。ルールが複雑とかプレイ時間が長いという意味じゃなくて重いんです。質量が。
なぜならコンポーネントの神殿駒がめちゃくちゃ豪華だから。

中までみっちり詰まったレジン製。ずっしりとした重みと、削りだした石を思わせる塗装。ボードゲームの良さには駒やカードなど、実体に触れる触覚の楽しみ*1というものがありまして、その点でこのゲームは数あるゲームの中でもトップクラスです。
初リリースは2002年で、当時のコンポーネントはこんなん。

(画像はBoard Game Geekより転載)
2015年の新版で桁違いに重厚な雰囲気になったのがお分かりいただけるかと思います。
なお、ボックスの重さを計ったら2.5kgありました。ボスが倒せない場合はレベルを上げてボックスで殴れ。相手は死ぬ。

プレイヤーはアステカの貴族となって、14世紀の中央アメリカに帝国を建設します。偉い人なので駒がサンバカーニバルみたいな帽子をかぶった形をしてます。

ボード右下に置かれたカルプリ(区画)トークンが皇帝からの命令。余はこのサイズに区切られた区画が見たいぞよ、というよくわかんねえ指示を出してくる皇帝なので貴族たちは我先にと区画整理をする羽目になります。

区画は青い運河タイルで区切って作る。運河で土地を所望のサイズに切り分けたら、対応するトークンを置いて名声ゲット。上のでっかい数字が区画のサイズで、左下の数字が区画を設立した人が手に入れる名声点。たまたま同じ区画にいるだけの他プレイヤーも右下の名声点がおこぼれでもらえます。

区切られた土地にはすかさず神殿を建築して影響力をアピール。その区画に建てた神殿の合計階数がそのまま影響力となって、ラウンド終了時に上位のプレイヤーから順にトークンに描かれた名声点がもらえます。このエリアだと1位~3位がそれぞれ12点/6点/3点というわけ。
こういう陣取りルールをボードゲームでは「エリアマジョリティ」と呼びますが、このゲームはそのマジョリティを競い合うエリアを自分たちで切り分けて作成していくところから始まるのがポイント。
毎手番、手持ちのアクションポイント(AP)を振り分けて運河を掘ったり神殿を建築したりという行動を取ることになりますが、運河を掘って区画を切り分けることに力を使い過ぎると、他のプレイヤーにうまうまとその区画をさらわれてしまうかもしれないという。
そうさせないためにも神殿・カルプリトークン・他のプレイヤーのいるマスは通過できないというルールを活用して、道を塞いで余計なAPを消費させるのが常套手段になります。

そこで効いてくるのが運河&橋。運河を超えて向こう岸に渡るためにかける橋ですが、運河が繋がっていれば橋から橋へ小舟で一気に移動できるルール。ときには外海も経由して、驚くほどの長距離も移動できます。
区画切り分けのための運河がゲーム後半では主要な移動手段となるわけです。神殿がじゃんじゃん建って陸路が移動しづらくなる代わりに水路を使ってダイナミックに動けるようになり、序盤と終盤でゲームの様相がガラッと変わる。うーん。実によくできている。テーマとルールの整合性も抜群。
四方を囲まれるなど、どうしても移動できない場合はAPをごっそり使ってワープもできます。アステカの貴族ならその程度のことはできて当然ですから違和感も全くありません。ありませんとも。

そして何より投了図が素晴らしい。神殿の林立する首都テノチティトラン。壮観!!
お互いえげつない妨害合戦の果てに完成した首都ですが、プレイヤー全員の共同作業で出来たと言えなくもないわけで。終わってみると勝ち負けがわりとどうでも良くなる感じがあります。
ルールは超シンプルで、それなのに考えどころが多く、遊んだ後の満足感が非常に高い。全く運が絡まないので初心者が楽しめないかというと、そうでもないのがまた良い。3人4人でプレーすると、それぞれの思惑がぶつかってかなり紛れが出るので、深い読みよりも臨機応変な対応が重要になってきます。そういうゲーム大好き。
コンポーネントが立派なだけに結構値は張りましたが、これは買って良かった。箱に比べてプレーは軽く、満足感は重量級。ボードゲーム遊んだったー!! というこの感覚はとてもとても良いものです。
*1:ネット麻雀の方が便利でも実物の方が楽しいというアレ